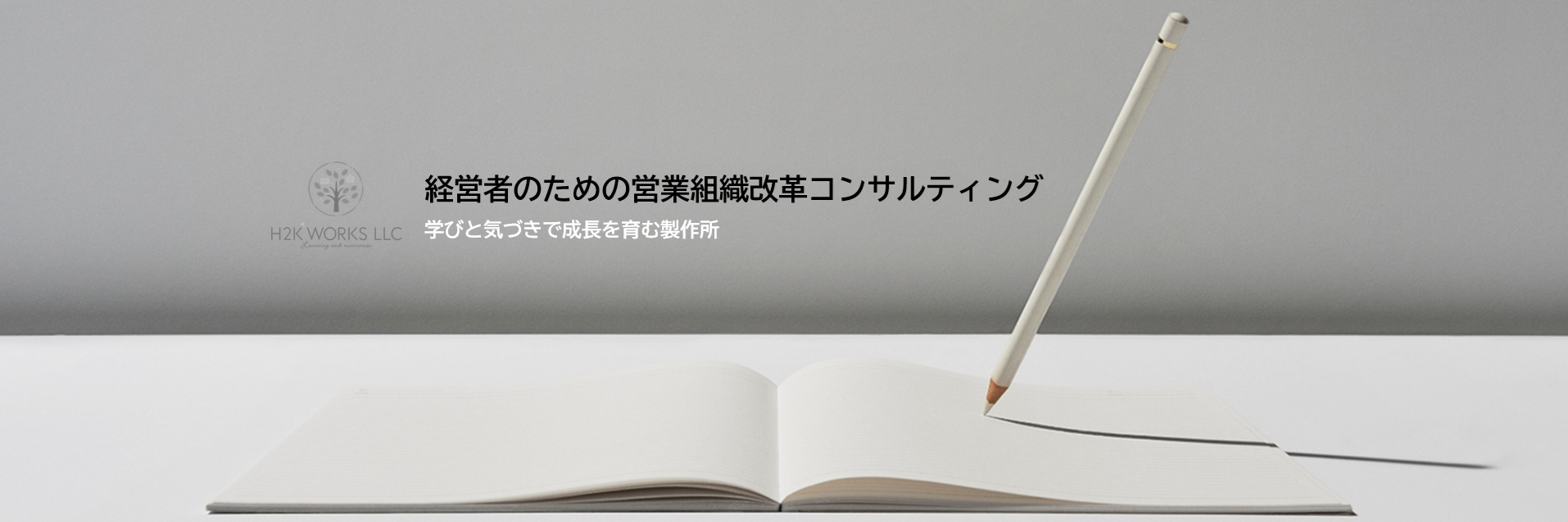「営業」概念を再定義する
「営業」という概念は、一般的には、英語の「Sell(売る)」「Sales(販売)」という意味で捉えられています。しかし私はこの概念を「経営」と同義と捉えています。なぜなら「営業」の語源を辿ると「世渡りの手段。生計を立てるための営み」を表す「スギワヒ/ナリワヒ」という和語に行きつくからです。
日本では明治以前、「個人」として世渡りや生計を立てることは行われていませんでした。基礎単位は「個人」ではなく「イエ(あるいはムラ)」だったからです。家業という言葉がありますが、家族が一体となって世渡りや生計を立ててきたわけです。明治以降「イエ」が「カイシャ(会社)」に形を変え、私たちも「カイシャ」に所属することで、世渡りや生計を立てるようになりました。
しかし、こうした行為は果たして「sell(売る)」「sales(販売)」という意味だけで表現できるものなのでしょうか?私はそうは思いません。ではどう表現すればよいか。「世渡りの手段。生計を立てるための営み」とは「経営」そのものなのです。
だからこそ「営業」という概念を単に「売る」「販売する」といった矮小化した意味で捉えるのではなく、カイシャに属する全員の営みだと「再定義」することこそ、今後の「会社経営」に必要不可欠な取り組みだと考えています。
エイチツーケーワークス合同会社 代表 脇 穂積
経営とは営業である
「営業」という言葉は日本の歴史上,いつ,どのような意味で登場したのか。大槻文彦(1881-91)によって編纂された日本初の近代国語辞典『言海』に,,「えいげふ(名)營業」の記述を確認することが出来,言葉の意味を「スギハヒ、ナリハヒ」と説明しています。現代語訳すると「世渡りの手段。生計を立てるための営み」となります。,江戸後期から明治初期にかけての漢語辞典を調べると,1869年出版の『漢語字類』に「ナリハヒ」という和語に対して「営業」という漢語が充てられていた。他にも,『布令字弁増補』2)1874年,『新編漢語辞林』3)1904年に「ナリハヒ(ナリワヒ)」という和語に対して「営業」の語が充てられていた。このことから,「営業」の語源は「漢語」であることが明らかとなった。
OUR TEAM
Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procras tinate users.Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procras tinate users.